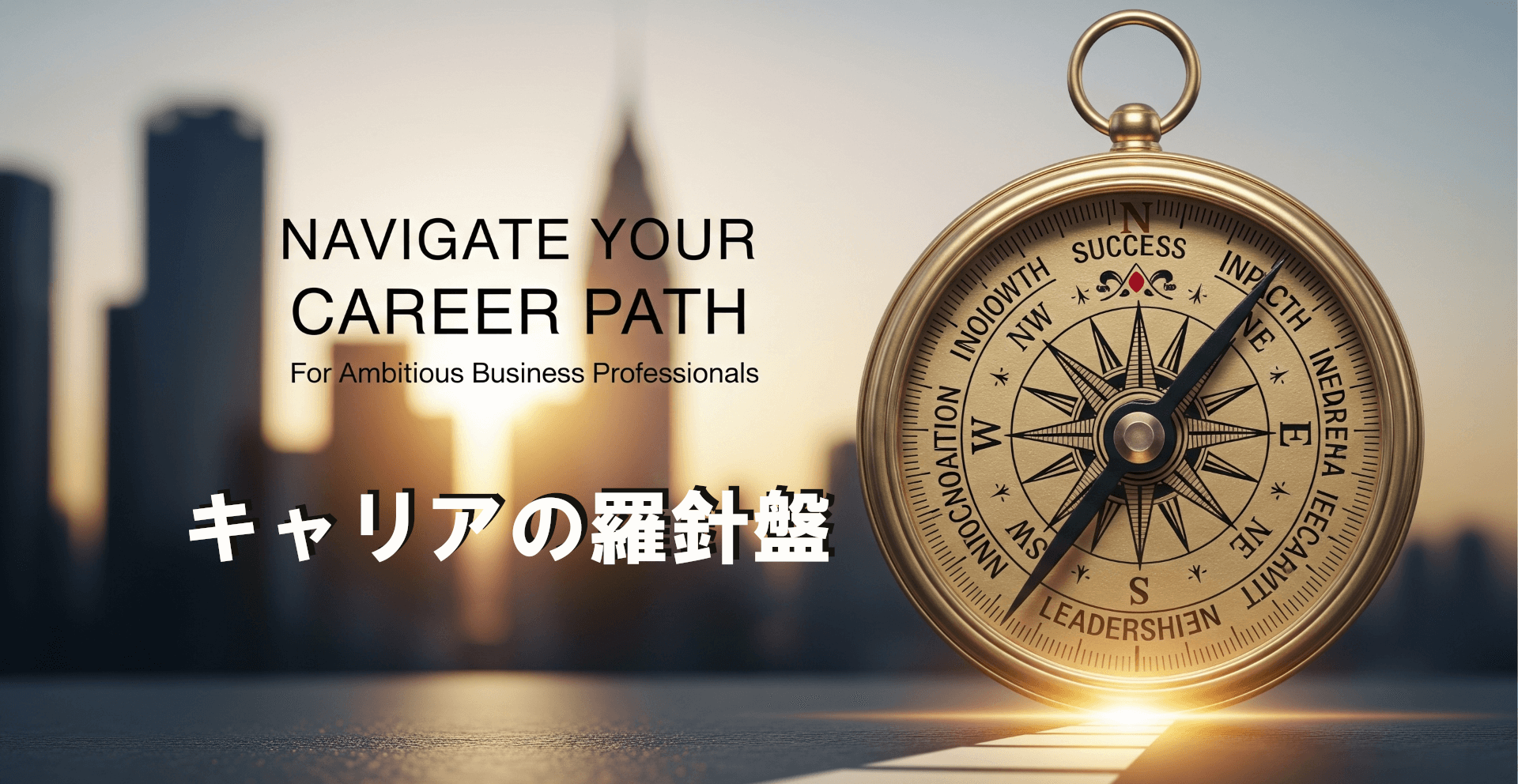「時間がない」「予算が足りない」「前例がない」…
かつての私は、何か新しい挑戦や困難な課題に直面するたび、無意識に「できない理由」を探し出す天才でした。まるで、自分の行動を制限する言い訳を見つけることが、仕事であるかのように。
しかし、ある時を境に、その思考の癖を意識的に変えてみました。具体的には、「できない理由」を探すのをやめ、「どうすればできるか?」という問いを自分に投げかけるようにしたのです。

結論から言います。この、たった一つの思考の転換が、私の仕事人生を劇的に変えました。停滞していたキャリアが動き出し、周囲からの信頼が厚くなり、そして何よりも、あれほど退屈で苦痛に感じていた仕事が、心から「楽しい」と思えるようになったのです。
この記事では、あなたの成長を阻害しているかもしれない「できない理由」を探す思考癖の正体と、それを克服し、「どうすればできるか?」を考えるポジティブな姿勢へ転換するための具体的な方法について、私の実体験を交えながらお話しします。
もし、あなたが今の仕事に行き詰まりを感じていたり、もっと成長したいと願っていたりするなら、この記事はきっとあなたのためのものです。
なぜ私たちは「できない理由」を探してしまうのか?
そもそも、なぜ私たちはこれほど巧みに「できない理由」を見つけ出してしまうのでしょうか。それは決して、あなたが怠惰だからとか、能力が低いからというわけではありません。多くの場合、人間の本能的な自己防衛機能が働いている結果なのです。
- 失敗への恐怖
人間は、本能的に失敗を恐れる生き物です。失敗すれば、評価が下がるかもしれない、恥をかくかもしれない、誰かに迷惑をかけるかもしれない。そうした未来の痛みを避けるために、「やらない」という選択を正当化する理由を探し始めます。つまり、「できない理由」は、挑戦というリスクから自分を守るための”盾”なのです。 -
現状維持バイアス(コンフォートゾーン)
私たちは変化を嫌い、慣れ親しんだ環境に留まろうとする傾向があります。これを心理学では「現状維持バイアス」と呼びます。新しい挑戦は、未知の領域へ足を踏み入れることであり、多大なエネルギーを消耗します。「今のままでも、まあ何とかなっている」という心地よいコンフォートゾーンに安住するために、「やらない」で済む理由を無意識に探してしまうのです。 -
完璧主義の罠
「やるからには完璧にこなさなければならない」という思い込みが強い人ほど、「できない理由」を探しがちです。100点満点が取れないのであれば、0点の方がマシだと考えてしまうのです。少しでも失敗する可能性があるなら、最初からやらない方が良い。その結果、ほんの些細な懸念点を「これは着手できない決定的な理由だ」と大袈裟に捉えてしまいます。

私自身、特に「失敗への恐怖」が強いタイプでした。上司に「この企画、本当に実現できるのか?」と問われた際に、自分の能力不足を悟られるのが怖くて、市場のデータや競合の動向を並べ立て、「現時点での実施は困難です」と、もっともらしい「できない理由」で自分を武装していました。しかし、その行動が、自らの成長の機会を次々と奪っていたことに、当時は気づけなかったのです。
「できない理由」を探し続けることの恐ろしい末路
「できない理由」を探す癖は、短期的にはあなたを失敗の痛みから守ってくれるかもしれません。しかし、長期的に見れば、それは非常に高くつく”保険”です。この思考を続けることで、あなたは以下のようなものを失っていくことになります。
- 成長機会の喪失
言うまでもなく、人は挑戦と失敗から最も多くを学びます。新しいプロジェクト、困難な目標、未経験の業務。これらはすべて、あなたのスキルセットを拡充し、視野を広げる絶好の機会です。これらを「できない」の一言で片付け続けることは、自らの成長の梯子を自ら外しているのと同じことです。 -
モチベーションの枯渇
「どうせ無理だ」「やっても無駄だ」という思考は、強力な自己暗示となります。これを繰り返すうちに、仕事そのものに対する情熱や好奇心は失われ、次第に「言われたことだけをこなす」指示待ちの状態に陥ります。仕事は「やらされるもの」となり、創造的な喜びは完全に失われてしまうでしょう。 -
周囲からの信頼の低下
あなたが常に「できない理由」を口にしていると、周りはあなたをどう見るでしょうか。「あの人に相談しても、どうせ否定的なことしか言わない」「挑戦しない人だ」というレッテルが貼られてしまいます。その結果、面白い仕事や重要なプロジェクトの話は、あなたの元には回ってこなくなります。前向きで「どうにかしよう」と奮闘する人の周りに、チャンスは集まるのです。 -
自己肯定感の低下
挑戦しないことで、成功体験を積む機会が失われます。成功体験の欠如は、自己肯定感の低下に直結します。「自分には何も成し遂げられない」という無力感が心を支配し、さらに挑戦を避けるという負のスパイラルに陥ってしまうのです。
かつての私は、まさにこのスパイラルにハマっていました。成長しない自分に焦りを感じながらも、新たな挑戦が怖い。だから「できない理由」で自分を守る。その結果、さらに自信を失っていく…。今思えば、本当に恐ろしい状態だったと思います。
「どうすればできるか?」思考への5つの転換ステップ
では、このネガティブな思考の連鎖を断ち切り、「どうすればできるか?」という建設的なマインドセットを手に入れるには、具体的にどうすればいいのでしょうか。私が実践し、効果を実感した5つのステップをご紹介します。

ステップ1:口癖を意識的に変える
思考は言葉に現れます。逆もまた然り。言葉を変えることで、思考を矯正することが可能です。
- 「でも」「だって」「どうせ」を封印する
これらは「できない理由」を探し始める際の三大キーワードです。まずは、これらの言葉を意識的に使わないようにしてみてください。会話や思考の中でこれらの言葉が出そうになったら、一度ぐっとこらえて、別の言葉に置き換える努力をします。 -
「できない」を「どうすればできるか?」に強制変換する
「〇〇だから、できない」という結論で思考を止めずに、「〇〇という制約がある。その上で、どうすればできるだろうか?」と、問いの形で思考を続ける癖をつけます。 -
(例)「時間がありません」 → 「どうすれば時間を捻出できるだろうか? 今のタスクの中で、やめられることや効率化できることはないか?」
- (例)「予算が足りません」 → 「この予算内で最大限の効果を出すにはどうすればいいか? 別の方法で目的を達成できないか?」
最初のうちは意識的な努力が必要ですが、繰り返すうちに、これがあなたの新しい思考のデフォルトになっていきます。
ステップ2:問題を細かく分解する
「新規事業を立ち上げろ」というような巨大な課題を目の前にすると、誰でも「できるわけがない」と感じてしまいます。これは、課題が大きすぎて、どこから手をつけていいか分からないからです。
そんな時は、その巨大な問題を、実行可能なレベルまで細かく分解してみましょう。
- (例)「新規事業を立ち上げる」
- 市場のニーズを調査する
- 競合他社のサービスを3つ分析する
- 事業のコンセプト案を3つ書き出す
- 関連部署のキーパーソンに15分だけヒアリングのアポを取る
- A4一枚で企画の骨子をまとめる
このように、一つひとつが「これならできそうだ」と思えるレベルの小さなタスクに分解することで、「できない」という巨大な壁は、「越えられる小さなハードル」の連続に変わります。最初の一歩を踏み出す心理的な抵抗が、劇的に下がるはずです。
ステップ3:制約を「創造性のトリガー」と捉える
「時間がない」「予算がない」「人がいない」。これらは「できない理由」の代表格ですが、見方を変えれば、新しいアイデアを生み出すための「創造性のトリガー」になり得ます。
潤沢なリソースがあれば、既存のやり方を踏襲するだけで事足りるかもしれません。しかし、制約があるからこそ、私たちは知恵を絞ります。
- 「予算がない」からこそ、お金をかけずに注目を集めるゲリラ的なマーケティング手法が生まれるかもしれません。
- 「人がいない」からこそ、徹底的に業務を自動化・効率化する画期的な仕組みが生まれるかもしれません。
- 「前例がない」からこそ、業界の常識を覆す全く新しいサービスが生まれるのです。
制約を「言い訳」にするのではなく、「ゲームの縛りプレイ」のように捉えてみる。「この縛りの中で、いかにしてクリアするか?」と考えることで、仕事は途端にクリエイティブな挑戦へと変わります。
ステップ4:臆せずに人を巻き込む
「どうすればできるか?」という問いは、一人で抱え込む必要は全くありません。むしろ、積極的に周囲を巻き込むことで、解決策は見つかりやすくなります。
- 「助けてください」と素直に言う
プライドが邪魔をして、人に頼ることをためらう人がいます。しかし、「この課題を解決したいのですが、〇〇の点で困っています。どうすればできるか、知恵を貸していただけませんか?」と正直に打ち明けることで、意外なほど多くの人が手を差し伸べてくれるものです。あなた一人の頭脳や経験には限界があります。他者の視点やスキルを借りることで、突破口は開けます。 -
壁打ち相手を見つける
信頼できる同僚や上司に、「ちょっと壁打ち相手になってもらえませんか?」と声をかけてみましょう。自分の考えを口に出して話しているうちに、頭の中が整理され、自分でも気づかなかった解決策が浮かび上がってくることは少なくありません。
「どうすればできるか?」という問いは、個人を強くするだけでなく、チームの結束力を高める魔法の言葉でもあるのです。
ステップ5:小さな「できた!」を記録し、祝う
思考の転換は一朝一夕にはいきません。だからこそ、小さな成功体験を積み重ね、自己効力感を育てていくことが不可欠です。
- 「できたことリスト」を作る
一日の終わりに、その日「できたこと」を3つ書き出すだけでも効果は絶大です。「〇〇について、どうすればできるか考え、△△というアイデアを出した」「〇〇さんに相談して、解決のヒントをもらった」など、どんなに些細なことでも構いません。 -
小さな成功を祝う
一つのタワーをクリアしたら、自分にご褒美をあげましょう。好きなお菓子を食べる、少し早く仕事を切り上げるなど、ささやかなことで十分です。この「祝う」という行為が、脳に「挑戦=快感」というポジティブな結びつきをインプットしてくれます。
この小さな「できた!」の積み重ねが、やがて「自分なら、どんな困難でも乗り越えられる」という揺るぎない自信へと繋がっていきます。
仕事が「クエスト」に変わった日
これらのステップを実践し始めてから、私の仕事に対する景色は一変しました。

以前は「面倒なタスク」としか思えなかった困難な課題が、まるでロールプレイングゲームの「クエスト」のように思えるようになったのです。
「予算不足という魔物を、知恵と工夫という武器でどう倒すか?」
「”前例がない”という呪文を、”前例を作る”という魔法でどう打ち破るか?」
「できない理由」を探していた頃は、ただただ憂鬱なだけだった仕事が、攻略法を探す楽しいゲームに変わりました。もちろん、全てのクエストが簡単にクリアできるわけではありません。しかし、「どうすればできるか?」と考え続ける限り、ゲームオーバーにはならないのです。
このマインドセットで仕事に取り組むようになってから、アウトプットの質は上がり、周囲からは「君に任せれば、何とかしてくれる」という信頼を得られるようになりました。何より、朝、仕事に向かう足取りが軽くなり、心の底から仕事を楽しんでいる自分に気づいた時の喜びは、今でも忘れられません。
最後に:あなたの未来を切り拓く、たった一つの問い
「できない理由」を探すのは簡単です。それは、現状維持という安全地帯に留まるための、最も手軽なチケットだからです。しかし、その先には、成長も、感動も、本当の楽しさもありません。
一方、「どうすればできるか?」と問う道は、いばらの道かもしれません。頭に汗をかき、時には失敗し、悔しい思いをすることもあるでしょう。
しかし、その道の先にこそ、新しい自分との出会いがあり、仲間からの信頼があり、想像もしていなかったような大きな成果が待っています。そして、困難を乗り越えた者だけが味わえる、最高の達成感と仕事の喜びがあるのです。
あなたの目の前にも、今、「できない」と感じる壁があるかもしれません。
さあ、今日からその壁の前で、こう自問してみてください。
「どうすれば、できるだろうか?」と。
その問いこそが、あなたの仕事を、そしてあなたの人生を、劇的に楽しく、豊かにする最強の鍵なのですから。